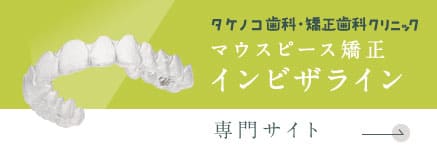歯の神経まで達した虫歯や、歯の根の感染が進行したケースで必要となる「根管治療」。難易度の高い治療であるため治療が長引くこともあり、「根管治療の期間はどれくらいかかるの?」と疑問に思う患者様も多いのではないでしょうか。根管治療の期間は、症状の重さや個々の歯の状態、歯科医師の治療技術によって異なります。
そこで本コラムでは、根管治療の期間について、軽度・中等度・重度のケースごとに解説するとともに、治療の流れや期間が変わる要因について詳しくご説明します。根管治療を受ける際の参考にしてください。
▼根管治療の期間はどのくらい?
はじめに、根管治療の期間を軽度・中等度・重度の3つのケースに分けて解説します。
◎軽度のケース(2~3回の通院)
初期段階の虫歯で、神経への影響が軽微な場合、根管内の感染が比較的少なく、清掃・消毒の処置も短時間で完了します。このケースでは、2~3回の通院で治療が完了することが一般的です。特に単純な根管形態の場合、迅速な治療が可能です。治療後は、再感染を防ぐために適切な予防措置を講じることが重要です。
◎中等度のケース(3〜5回の通院)
虫歯が進行し、神経が感染している場合や、根管の内部に細菌が繁殖している場合は、3〜5回の通院が必要になることがあります。この段階では、根管内を徹底的に清掃・消毒し、感染を完全に除去することが求められます。治療には薬剤を用いた長期的な消毒が必要な場合もあり、再発を防ぐために治療間隔を空けながら慎重に進めることが大切です。また、神経の損傷度合いや根管の複雑さにより、治療期間が左右されることもあります。
◎重度のケース(5回以上の通院)
根の先端に膿が溜まる「根尖性歯周炎」や、過去に根管治療を受けた歯の再治療が必要な場合は、治療が複雑化し、5回以上の通院が必要になることが多いです。特に、歯根が湾曲している場合や、感染が広範囲に及んでいる場合、治療には時間がかかります。また、難治性の感染症例では、抗菌薬を併用することや、外科的処置(歯根端切除術)を検討することもあります。根管治療では治療期間の延長を最小限に抑えるために、的確な診断と適切な治療計画の立案が不可欠です。
▼根管治療の流れ
続いては、根管治療の流れを解説します。
1.診査・診断
まず、歯科医師がX線やCT撮影、口腔内診査を行い、根管治療が必要かどうかを判断します。特にCT撮影では、従来のX線では見えなかった根管の複雑な構造や、感染の広がりを詳細に把握することができます。根の状態を詳しく分析し、根管の本数や形状を確認することで、適切な治療計画を立てることができます。
2.麻酔と感染部分の除去
治療の際は局所麻酔を行い、痛みを抑えながら治療を進めます。特に根管内の感染が進行している場合、炎症によって麻酔の効果が低下することがあります。そのため、場合によっては麻酔の種類や投与量を調整し、最大限の鎮痛効果を得られるように工夫します。その後、虫歯の部分を削り、感染した神経や歯質を取り除きます。感染が進んでいる場合は、根管内の清掃に時間をかける必要があります。
3.根管の清掃・消毒
根管内の細菌を徹底的に除去し、消毒を行います。細菌の繁殖を防ぐために、薬剤を用いることもあります。最新の根管治療では、超音波洗浄やレーザーを使用することで、従来よりも精度の高い清掃が可能になっています。これにより、根管の隅々まで細菌を除去し、治療成功率を向上させることができます。症状によっては、数回にわたって消毒が必要になります。
4.根管充填
根管内が清潔になったら、再感染を防ぐために根管充填材を詰めます。近年では、生体親和性の高いMTA(ミネラルトリオキサイドアグリゲート)を使用することが増えており、従来の材料よりも封鎖性が高く、根管内の細菌侵入を防ぐ効果が期待されています。この処置により、歯の内部に細菌が侵入するのを防ぎ、根管治療後の再発リスクを低減します。
5.被せ物の装着
根管治療後は、歯を補強するために被せ物(クラウン)を装着することが一般的です。クラウンの素材には、金属・セラミック・ジルコニアなどがあり、機能性や審美性を考慮しながら選択します。特に奥歯では、咬合圧(噛む力)が強いため、耐久性のあるクラウンを選ぶことが重要です。
また、歯の破折を防ぐために、歯の内部にファイバーコアと呼ばれる補強材を入れることもあります。被せ物を適切に装着することで、噛み合わせの安定を保ち、歯を長持ちさせることができます。もちろん、保険診療のメタルクラウン(銀歯)でも歯の機能はある程度まで回復できますが、見た目が悪かったり、金属アレルギーのリスクが合ったりするなど、欠点が目立つ点に注意が必要です。
▼根管治療の期間は歯科医師の技術で変わる?
根管治療の期間は、歯科医師の技術や使用する機器によっても大きく左右されます。例えば、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いることで、肉眼では確認しにくい微細な根管内の状態を詳細に観察しながら正確な処置が可能になります。根管の形態は歯によって異なり、特に臼歯では複雑な分岐が存在するため、視認性の向上は治療の正確性に直結します。その結果、不適切な処置による再治療のリスクを減らし、無駄な処置を最小限に抑えることで治療期間を短縮できる場合があります。
また、根管治療にはラバーダムと呼ばれる防湿シートの使用が推奨されています。これにより、唾液による細菌感染を防ぎ、治療の成功率が高まります。さらに、ニッケルチタン製の柔軟な根管治療器具を用いることで、湾曲した根管にも適応しやすく、従来よりもスムーズかつ短期間で治療を完了できるケースも増えています。
加えて、歯科医師の経験や技術レベルも治療のスムーズさを大きく左右します。例えば、根管の解剖学的構造を正確に把握し、適切な形成・洗浄を行うことで、細菌の残存を防ぐことができます。経験豊富な歯科医師であれば、治療計画を効率的に進めることができるため、短期間で根管治療を完了できる可能性が高くなります。一方で、未熟な処置や不十分な消毒は、根尖病変の再発リスクを高め、結果的に治療期間が延びることになります。
したがって、根管治療を受ける際は、歯科医院がどのような技術や機器を導入しているか、担当する歯科医師の経験が豊富であるかを確認することが重要です。信頼できる医院を選ぶことで、治療の成功率を高め、できるだけ短期間で適切な治療を受けることが可能になります。
▼まとめ
根管治療の期間は、症状の重さによって異なり、軽度の場合は2~3回の通院、中等度では3〜5回、重度では5回以上の通院が必要になることがあります。また、根管治療の流れとして、診査・診断、感染部分の除去、根管の清掃・消毒、根管充填、被せ物の装着というステップを経て治療が完了します。
さらに、歯科医師の技術や治療設備によっても治療期間が変わることがあるため、信頼できる歯科医院で適切な治療を受けることが大切です。草加市のタケノコ歯科・矯正歯科クリニックでは、患者様にとって最適な治療を提供できるよう努めております。根管治療について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。