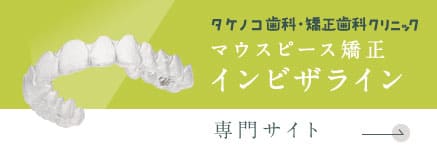歯の健康を維持するためには、定期的な歯科検診が欠かせません。しかし、「歯医者でどのような検査が行われるのか分からない」「痛みがあるのでは?」と不安を感じる患者様も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、歯科医院で行われる各種検査について、歯科医師が詳しく解説します。視診や触診といった基本的なものから、レントゲンやCT検査などの高度な検査まで、それぞれの特徴や目的を分かりやすくご紹介します。また、歯科の検査は痛いのかどうかについても触れていきます。
歯医者での検査を正しく理解し、安心して受診できるようにしましょう。
▼歯医者の検査の種類と特徴
歯医者では、次に挙げる種類の検査を行うことがあります。それぞれの特徴を簡単に解説します。歯医者の検査は、患者様の症状によって必要となるものが大きく変わるため、生涯で一度も受けない検査もあることでしょう。
◎視診
視診は、歯科医師が患者様の口腔内を目視でチェックする基本的な検査です。虫歯の有無や進行度、歯茎の炎症、噛み合わせの異常などを確認します。小さな虫歯や歯のヒビは、光の反射や変色によって判別することが可能です。また、歯の表面だけでなく、歯の形態や歯肉の状態も診ることで、全体的な口腔の健康状態を評価できます。
【視診で分かること】
・虫歯の有無や進行度
・歯茎の腫れや炎症の有無
・詰め物や被せ物の状態
・歯の摩耗や破折の有無
・口腔粘膜の異常(口内炎や腫瘍の疑いなど)
【必要となる症例】
・定期検診時のチェック
・虫歯の疑いがある場合
・歯茎が腫れている場合
・噛み合わせの異常がある場合
◎触診
触診では、歯科医師が指や器具を使って歯や歯茎の状態を確認します。歯の動揺(ぐらつき)や、歯茎の腫れ、圧痛の有無をチェックすることで、歯周病の進行度や隠れた炎症を把握できます。特に、歯の根元に異常な圧痛がある場合、根尖病変(根の先に膿がたまる状態)の可能性を示唆することがあります。
【触診で分かること】
・歯のぐらつきの程度
・歯茎の腫れや炎症
・噛み合わせ時の違和感
・口腔内のしこりや異常な硬結
【必要となる症例】
・歯周病が疑われる場合
・歯の揺れが気になる場合
・痛みの原因を調べる場合
・口腔がんのスクリーニング
◎歯周組織検査
歯周組織検査は、歯周病の進行状況を調べるための検査です。プローブと呼ばれる器具を用いて歯周ポケットの深さを測定し、歯茎の健康状態を確認します。また、出血の有無やプラークの付着状況も記録し、歯周病の進行度を総合的に診断します。
【歯周組織検査で分かること】
・歯周病の進行度
・歯茎の出血や炎症の有無
・歯を支える骨の状態
・プラークや歯石の付着状況
【必要となる症例】
・歯茎の腫れや出血がある場合
・口臭が気になる場合
・歯がぐらつく場合
・歯周病のリスク評価
◎電気歯髄診
電気歯髄診は、歯の神経が生きているかどうかを調べる検査です。微弱な電流を歯に流し、反応を確認することで神経の状態を判断します。
【電気歯髄診で分かること】
・歯の神経の生死
・神経がダメージを受けているかどうか
【必要となる症例】
・強い痛みがある場合
・事故などで歯をぶつけた場合
・虫歯が神経まで達している可能性がある場合
◎レントゲン検査
レントゲン検査は、歯や顎の骨の内部を詳しく見るための検査です。虫歯の進行度や歯の根の状態、親知らずの位置などを正確に確認できます。
【レントゲン検査で分かること】
・目に見えない虫歯の進行状況
・歯の根の状態や膿の有無
・親知らずの位置
【必要となる症例】
・虫歯の診断
・親知らずの抜歯前
・根管治療(神経の治療)が必要な場合
◎CT検査
CT検査は、3D画像で歯や顎の骨を詳細に撮影する高度な検査です。インプラント治療や親知らずの抜歯など、精密な診断が求められる場合に使用されます。
【CT検査で分かること】
・顎の骨の厚みや状態
・神経の位置関係
・歯の破折(ひび割れ)の有無
【必要となる症例】
・インプラント治療
・難しい親知らずの抜歯
・外傷による歯の損傷
◎唾液検査
唾液検査は、虫歯や歯周病のリスクを調べるために行われます。唾液の量やpH、細菌の数を測定し、個々の口腔環境を評価します。
【唾液検査で分かること】
・虫歯や歯周病のリスク
・口腔内の細菌の状態
・唾液の分泌量
【必要となる症例】
・虫歯が多い方
・口が乾く症状がある方
・予防歯科を希望する方
◎噛み合わせの検査
噛み合わせの検査では、上下の歯が適切に接触しているかを確認します。噛み合わせの異常は、顎関節症や歯のすり減りの原因となるため、早期発見が重要です。
【噛み合わせの検査で分かること】
・噛み合わせのずれ
・顎関節の異常
・歯ぎしりや食いしばりの影響
【必要となる症例】
・顎の痛みがある場合
・噛みにくさを感じる場合
・歯ぎしりの疑いがある場合
▼歯医者の検査は痛くない?
「歯医者の検査は痛いのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、ほとんどの検査は痛みを伴わず、安心して受けることができます。視診や触診、レントゲン検査、唾液検査は、基本的に無痛であり、患者様の負担を最小限に抑えた方法で行われます。
ただし、歯周組織検査や電気歯髄診のように、歯や歯茎の状態をより詳しく調べる検査では、歯茎が炎症を起こしている場合や神経が過敏な場合に、軽い違和感を覚えることがあります。歯周組織検査では、歯周ポケットの深さを測る際にプローブと呼ばれる器具を用いるため、炎症が強いとチクっとした刺激を感じることがあります。しかし、これは短時間で終わるため、強い痛みを伴うことはほとんどありません。また、電気歯髄診では微弱な電流を流すことで神経の反応を確認しますが、一般的には軽いピリッとした感覚がある程度で、痛みと呼べるものではありません。
さらに、噛み合わせの検査やCT検査なども、痛みを伴わずに受けることができます。噛み合わせの不具合がある場合、長期間放置すると顎関節症のリスクが高まるため、検査を受けることが大切です。唾液検査も、簡単な採取方法で行われ、痛みを感じることはありません。
検査中に痛みを感じた場合は、遠慮せずに歯科医師に伝えましょう。麻酔の使用や検査方法の調整により、痛みを最小限に抑えることが可能です。患者様がリラックスして検査を受けられるように、当院では丁寧な説明と適切な対応を心掛けています。
▼まとめ
今回は、歯医者で行う検査の種類や特徴、検査を行うことによってわかることなどを解説しました。歯医者で行う検査にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる目的や特徴があります。視診や触診、歯周組織検査などの基本的な検査から、レントゲンやCT検査といった高度なものまで、症状や必要性に応じて適切な検査が行われます。
検査は、虫歯や歯周病などのトラブルを早期に発見し、適切な治療を行うために不可欠です。また、噛み合わせの異常や口腔環境のリスク評価にも役立ちます。
「検査は痛いのでは?」と心配される方もいるかもしれませんが、多くの検査は無痛で受けられます。痛みが気になる場合は、歯科医師に相談しながら進めることで、安心して検査を受けることができます。
当院では、患者様の負担を最小限に抑えながら、正確な診断を行うことを心掛けています。お口の健康を守るために、定期的な検査を受けることをおすすめします。