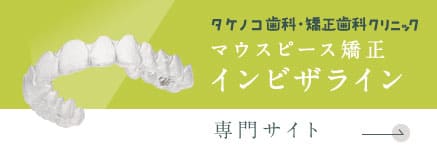歯科医院で診察を受ける際、レントゲン撮影を勧められることがあります。しかし、「放射線を浴びることで健康に影響はないのか?」と不安に感じる患者様もいらっしゃるかもしれません。特に、お子様の診療でレントゲンを撮影する際は、安全性について慎重に考えることが大切です。
◎結論から
歯科医師として申し上げると、歯科医院で行うレントゲン撮影は非常に安全性が高く、医療上のメリットが大きい検査です。被ばく量はごくわずかで、日常生活で自然に浴びる放射線量と比べても問題のないレベルに抑えられています。さらに、口腔内の状態を詳細に把握することで、虫歯や歯周病の早期発見・治療につながるため、適切に活用することが望ましいといえます。
そこで本記事では、歯科医院で使用されるレントゲンの種類や特徴、安全性についての解説を行い、安心して検査を受けていただけるよう詳しくご説明します。
▼歯科医院のレントゲンの種類と特徴
歯科医院で使用されるレントゲンには、主に「デンタル」と「パノラマ」の2種類があります。それぞれの特徴や被ばく量について解説します。
◎デンタルレントゲン
デンタルレントゲンは、歯の部分的な状態を詳細に確認するための小型のレントゲンです。1~3本程度の歯を撮影でき、虫歯の進行状態や歯の根の状態、歯茎の健康状態を確認する際に使用されます。
このレントゲンの被ばく量は非常に少なく、1回の撮影で0.01~0.02ミリシーベルト程度とされています。これは、自然界から1日で受ける放射線量(約0.007~0.01ミリシーベルト)とほぼ同等の値であり、健康への影響はほとんどありません。
◎パノラマレントゲン
パノラマレントゲンは、口腔全体を一度に撮影できるレントゲンです。歯列全体の状態、歯の生え方、顎の骨の状態などを確認するために使用されます。特に、矯正治療や親知らずの診断、顎関節症の評価に役立ちます。
被ばく量は0.02~0.03ミリシーベルト程度であり、デンタルレントゲンよりやや多いものの、やはり日常生活で受ける自然放射線の量と比較しても問題のない範囲です。
▼歯科医院のレントゲンは安全性が高い
歯科医院で使用されるレントゲンの安全性について、以下の点から詳しく解説します。
◎日常生活で受ける放射線量との比較
私たちは日常生活の中で、自然界から放射線を常に浴びています。これは、宇宙線、大気中のラドン、地殻からの放射線などの影響によるものです。具体的には、
・1年間に受ける自然放射線量は約2.4ミリシーベルト
・東京~ニューヨーク間の航空機移動で約0.1ミリシーベルト(高度が高いため放射線量が増加)
・胸部レントゲン撮影(医科)で約0.1ミリシーベルト
これらの数値と比較すると、歯科のレントゲンで受ける被ばく量は極めて低く、安全性が高いことが分かります。さらに、地球の地域によっては自然放射線量が異なり、高地ではより多くの放射線を受けることになります。しかし、これが人体に影響を及ぼすことはほとんどないとされており、歯科のレントゲンも同様に安全であるといえます。
◎医科のCT・レントゲンとの比較
医科で使用されるCTやX線検査は、全身を対象とするものが多く、それに伴い被ばく量も増加します。具体的な被ばく量を比較すると以下の通りです。
胸部CT:約7ミリシーベルト(肺全体を詳細に撮影)
腹部CT:約10ミリシーベルト(臓器や血管の評価に使用)
歯科のデンタルレントゲン:0.01~0.02ミリシーベルト(特定の歯を詳細に撮影)
歯科のパノラマレントゲン:0.02~0.03ミリシーベルト(歯列全体を撮影)
歯科のレントゲンは撮影範囲が狭いため、他の医療用レントゲンと比べても放射線量が非常に少なく、安全性が高いことが分かります。
◎口腔内に限定されるため影響が少ない
歯科のレントゲンは、撮影範囲が口腔内に限定されるため、全身への影響はほぼありません。加えて、撮影時には鉛製の防護エプロンを着用することで、さらに被ばくを低減することが可能です。特に妊娠中の患者様や小さなお子様には、安全対策として適切な防護措置を行うことで、放射線によるリスクを最小限に抑えることができます。
また、近年の歯科用レントゲン機器はデジタル化が進み、従来のフィルムタイプのレントゲンに比べて放射線量が大幅に低減されています。これにより、より安全な診療が可能となっています。
▼歯科医院のレントゲンで注意すべき点
歯科医院のレントゲンは安全性が高いですが、以下の点には注意が必要です。
1.妊娠中の撮影は事前に相談する
妊娠中の方は、胎児への影響を考慮してレントゲン撮影を避けることが望ましい場合があります。放射線は胎児に対して特に感受性が高い初期の発育段階に影響を与える可能性があります。しかし、歯科のレントゲンは放射線が口腔内に限定されており、お腹から遠いため、一般的に胎児への影響は極めて低いとされています。
また、鉛製の防護エプロンを使用することで、さらに安全性を確保できます。妊娠が判明している、または妊娠の可能性がある方は、撮影前に歯科医師に相談し、安全な診療計画を立てましょう。
2.不要なレントゲンを避ける
歯科レントゲンは正確な診断のために重要ですが、過剰な被ばくを防ぐためにも適切な頻度で行うことが大切です。歯科医師は過去のレントゲン画像を参考にしながら、診断に必要な最小限の撮影を行います。
患者様自身も、過去に撮影したレントゲン画像を保管し、診療時に提示することで不要な撮影を避けることができます。特に、定期的に歯科医院を受診している方は、レントゲンの履歴を把握しておくと良いでしょう。
3.防護エプロンと甲状腺プロテクターの活用
レントゲン撮影時には、防護エプロンを着用することで不要な放射線の影響を軽減できます。特に、お子様や妊娠中の方には積極的に防護措置を講じることが推奨されます。
さらに、甲状腺は放射線の影響を受けやすい臓器のひとつであるため、甲状腺プロテクター(鉛入りの首元カバー)を使用することで、安全性をさらに向上させることが可能です。特に成長期のお子様や、甲状腺機能に不安を抱える方には、積極的な使用が勧められます。ただし、甲状腺プロテクターまで導入している歯科医院はそれほど多くはありません。
近年の歯科用レントゲン機器は、デジタル化によって放射線量が大幅に低減されており、安全性が向上しています。しかし、患者様が安心して受診できるよう、最適な診断と防護策を組み合わせることが重要です。
▼まとめ
今回は、歯科医院で行うレントゲンの健康被害や安全性について、歯科医師の立場から解説しました。歯科医院で行うレントゲン撮影は、口腔内の詳細な情報を把握し、虫歯や歯周病、噛み合わせの異常などを早期に発見するために重要な検査です。被ばく量は非常に少なく、日常生活で受ける自然放射線と比較しても安全性が高いことが分かります。
また、歯科のレントゲンは撮影範囲が限られており、適切な防護対策を行うことでリスクを最小限に抑えることができます。妊娠中の方やお子様の撮影については、歯科医師に相談することで適切な対応が可能です。
当院では、患者様が安心して診療を受けられるよう、適切な診断のもとでレントゲンを活用し、安全な治療を提供しております。何か不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。